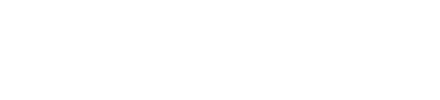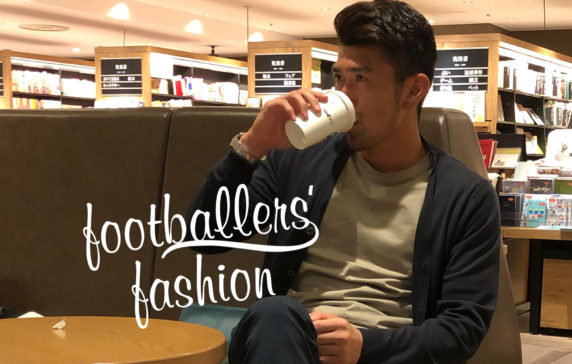-

サッカー専門トレーナーX
J1チーム専属トレーナーを経て独立し、現在Jリーガー・欧州プロサッカー選手たちを中心に様々な種目のトップアスリートのパーソナルサポートを展開。これまで国内外のプロサッカー選手、約200名のコンディショニングに関わってきた経験をもとに、コンディショニングを多元的に追求し続けています。
「ケガを知って強くなる!」シリーズでは前回までに、現代医学的なセオリーに沿ったケガの急性期と慢性期の痛みの仕組みについての解釈を、Xの経験を加えて駆け足でお伝えしてきました。
ですが、この仕事に携わって25年。『痛み』について日々考え、試行錯誤を繰り返してきた中でセオリー通りだったことはどのくらいあったのかと考えると、全体のわずか10%ほどです。そこで、ここからは残りの90%のケガの痛みについてのお話をしていきます。
今回の主題となるのは、コラム16で紹介した4つ目の痛み、『心因性疼痛(心理的な状態により影響を受け、神経や体そのものは傷害されていないのに感じる痛み)』です。これを介さない痛みはほぼ存在しません。この「心因性疼痛」を掘り下げていこうと思います。
痛みについて最先端科学研究をする政界的な研究機関『国際疼痛学会』は、痛みの定義について下記のように発表しています。
「実際に何らかの組織損傷が起こったとき、または組織損傷を起こす可能性があるとき、あるいはそのような損傷の際に表現される、不快な感覚や不快な情動体験」
“An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage”
つまり、痛みは感覚と感情であり、組織の損傷の有無に関わらず、本人が痛いと認知すれば痛みが存在するということです。反対に、損傷があっても本人が痛くないのなら、痛みはないということになります。それもあって、痛み止め薬には強い『プラセボ効果』(注:効き目のある薬を服用していると本人が思い込めば、中身が実はラムネだとしても痛みが改善されること)が見られることが多いのです。このため、新しい薬の開発では、なかなか偽薬(プラセボ)以上の鎮痛効果を期待することが難しかったりもするようです。
そうした定義をもとに、いま一度『痛み』の定義をまとめると2つに分類できます。
① ケガを伴う痛み:痛みとなる刺激が脳で認知され、さらに不快な感情を持ち、情動体験(怒り、恐れ、悲しみなど、一時的で急激な感情の動き)が引き起こされることにより生じる。
② ケガを伴わない痛み:痛みとなるケガや刺激はないにもかかわらず、不快感・情動体験が強く引き出されることにより生じる。
人間が『痛み』を認知するメカニズムについての研究は日々進んできている最中ですが、少なくとも、痛みは知覚・情動・認知に係わる脳の領域で処理される過程で生まれる複雑な感覚です。つまり、痛みとは原始的な感覚であると同時に、とても高度な感覚でもあるということです。
この続きはまた次回、より掘り下げてお伝えしていきます。