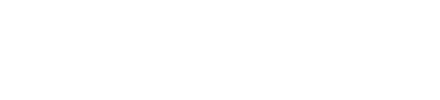「日本のサッカーを強くしたい」「なぜドイツはあんなに勝負強いのか」。そんな思いや疑問を胸にドイツに渡った。大きな自己変革が伴う街クラブでの指導を経て、また日本代表選手の通訳をしながらプロのトップチームの監督の手法を学び、現在はオーストリアのザルツブルグでU-16チームのコーチを務める。サッカー大国、ドイツで学んだ多くのことについてお話をうかがった。
ーLucero京都の樋口健策監督からのご紹介での登場となります。樋口さんとの関係を教えてください。
宮沢 僕は、びわこ成蹊スポーツ大学出身なのですが、樋口監督は、そこのサッカー部の1年後輩にあたります。今も連絡は取りあっていて、僕が日本に帰国した際に、彼のクラブチームで指導させてもらったりしています。彼は『優しい人間』なので、その人柄に魅力を感じて選手が、保護者が、スタッフがついてくるんだろうな、ということは想像できます。また彼は「サッカーへの情熱」と「人への愛情」が深いので、彼に指導される選手、子どもたちはサッカーだけではなく、人として成長できる学びが、日常生活・クラブの活動を通してあるのではかと思います。
ー宮沢さんはなぜ、指導者を目指したのでしょうか?
宮沢 サッカーが好きだということがまずは一つ。その上で、プレーしている時から指導者目線というんですかね、指導者を常に意識していたように思います。
ーそれは高校、大学でプレーしている時のことですか?
宮沢 いいえ、小学校の時からです。
ー小学生が指導者目線を持ちながらプレーヤーするというのは珍しい!
宮沢 その時のコーチの影響とチームの強さに影響していると思います。弱小のチームだったため、頭を使うこと、いろいろなことを考えながらプレーすることの面白さを教えてくれたことが大きかったですね。そのコーチは小辻一巳さんという方で、今は大学の方で教えながら、さまざまなチームでも指導をされているようです。
ー大学卒業後にドイツに渡りました。海外の中でドイツを選んだ理由は?
宮沢 19歳、20歳くらいの僕の中にあったドイツ・サッカーのイメージはとにかく「強い」ということ。うまいとか、ではなく、強い。なぜ、ドイツという国は国際舞台で勝利という結果を残して来たのだろう、と不思議に思ったところから、ドイツで指導について学べば、強さの理由が分かるかもしれないと考えました。それがドイツを選んだ理由です。

ードイツに渡った最初のころの生活は?
宮沢 日本で少しは勉強しましたが、ほとんどドイツ語をしゃべれないレベルだったので、語学学校に通いました。朝は日本料理のお店でバイトをさせてもらって、午前中は語学学校に通い、午後からはサッカークラブの指導者見習いの形で指導現場に立たせてもらって、夜は自宅でドイツ語の勉強。それを3年くらい続けました。
ー指導者見習いは街の少年チームですか? まだドイツ語がしゃべることができないのに?
宮沢 ジュニア・チームです。あくまで見習いなので、練習グラウンドに立たせてもらって、見て、言葉を覚えて、メモして、あとは雑用をする。そんな感じです。とにかく現場で言葉を覚えてしまおう、と。その気合いを評価して頂き、翌年からU8を指導させて頂けるようになりました。
ーケルン・スポーツ大学でも学ばれたんですよね?
宮沢 そういう生活をして3年目、ビザの切り替え時期になって、労働ビザか学業ビザかの選択をする時に、労働ビザにするとサッカーの指導を学ぶ時間がなくなると考えて、学業ビザを選択しました。それでケルン・スポーツ大学の入学試験を受けて、入学しました。でも、そこで学ぶことだけではなく、人脈づくり・情報収集をメインの目的として入りました。ですから、卒業はしておりません。入学してからは、一日二コマの授業の選択にとどめて、サッカーの指導や、試合を観に行く時間をつくりました。とても充実した学業生活でしたね。結果的に4年半くらい通って、当初の目的通り、多くの人と知り合えましたし、多くの情報を手に入れることができたと思います。
ー大学に通いながら街クラブの指導を? そのクラブはどういうクラブですか?
宮沢 それがメイン、人生の軸でしたから。クラブはケルン・スポーツ大学の隣で活動していた街クラブ。その代表者が、FCケルンのアカデミーダイレクターも務めていたので、その街クラブは、FCケルンのパートナークラブの一つでした。普通の街クラブよりはうまい選手が所属、それよりもうまい選手がFCケルンのアカデミーに引き抜かれていく感じですね。そのクラブはU-17まであって、僕はU-8の指導から始まって、最終的にはU-13以外のU-14までのチームすべての指導を経験することができました。

ーそこでの指導はどうでしたか?
宮沢 「なぜだろう」「どうやったらうまくいくんだろう」、とすごく考えて指導しました。日本でやってきた、経験してきた指導がなかなか通用しない。すべてを理論的に再構築しなくちゃいけなかったんです。でも、とても充実していて、めちゃくちゃ面白い時間になりました。
ー例えば、どういう再構築が必要だったのでしょうか。
宮沢 まず練習時間が短い。当時でいうと、例えばU-9の場合だと1時間。ウォーミングアップも含めてです。でも僕は20分から30分のゲームを必ず行なうと決めていたので、そうなると残りは30分くらい。ですから、日本でやっていた二人組の対面パスなどの基礎練習はやる時間がない。じゃあ、どうやってゲームに近いパス練習をするのかと考えていくようになると、今まで自分がプレーヤーとしてもやって来た15分の対面パスをしていたことに疑問を覚えるんです。それで自分の技術は高まった、と思っていたのに、実はそうではなかったのではないか、と。そこでいろいろと考えることで、2対1で、相手がいる状況の中、つまり試合に近いような状況の中で対面パスの練習のような状況をつくりだしてみよう、と考える。そうすれば、実戦的な練習でありながら、基礎技術の習得にもつながるのではないか、と。そして、退屈そうに見える対面パスを選手が家で練習したくなるような工夫をしたり、実践的な練習の前の段階の自主練習の必要性を気づかせてあげることで、再構築に対応していったと思います。
ーしかし、小学生のころから続けてきた練習に疑問を持つということは、自己否定とは言わないまでも、精神的にも苦しい大変な世界に足を踏み込みましたね?
宮沢 実は、そこが指導者として海外に出て行く一つのメリットだと思います。「今まで自分がやってきたことが正しいことだったのか」と、思い直せる、そのきっかけと時間を海外に来れば手にできるということ。もちろん、日本で指導する、指導を学ぶことが悪いと言いたいわけではありません。違う文化に飛び込んで、今まで正しいと思っていたことを全否定されることから始まると、そこに新たな自分が生まれる。それも一つの進歩だと僕は思います。

ーFCケルンにおいて長澤和輝選手(現・浦和レッズ所属)と大迫勇也選手(現・ベルダー・ブレーメン所属)の通訳を務めるようになった経緯を教えてください。
宮沢 偶然から始まっているんです。長澤選手の高校の先輩であり、僕の後輩にあたる友人とプライベートでケルンの公園でボールを蹴っていたら、ランニング中の長澤選手がたまたま通りかかって「日本語が聞こえたから」と言って、僕らに話しかけてきたんです。そこでまず長澤選手と知り合ったんですね。その後、FCケルンが長澤選手の通訳として良い人材がいないかと、ケルン・スポーツ大学の教授のところに問い合わせました。そこで数名を推薦してくれたので、クラブに面接に行くと、長澤選手とも面接をして「前に会いましたよね」という話の流れで、スッと話がまとまったんです。
ー通訳は指導者としてプラスになると考えて引き受けたのでしょうかうか?
宮沢 通訳は監督が言っていることをすべて聞けるので、ものすごく為になると思いました。ただし、通訳というのは、監督やコーチの立ち位置とは雲泥の差で、責任の重さがまったく違うので、通訳は前に出たくても出たらいけない時があります。逆に指導者は前に出なければいけない時があって、その立場をわきまえるなら、通訳であっても指導者になるために必要ないろいろなことが絶対に学べると思います。
ー当時、ケルンの監督を務めていたのはオーストリア人のペーター・シュテーガー監督でしたよね。どんなことを学びましたか?
宮沢 シュテーガーさんが一番大事にしていたのは、選手やスタッフのモチベーションや感情、情熱でした。細かいことをあまり言わない方だったので、選手はのびのびとプレーできていたように感じました。私はシュテーガー監督からは個の能力をいかに引き出すか、というところで勉強させていただきました。通訳としての僕の仕事もやりやすいようにサポートして頂きました。また他方面で褒めてもらい、輪の中に入れたりする気配りも含めて、「監督のために頑張らなければ」と思える監督でした。
ーザルツブルクで、南野拓実選手と奥川雅也選手の通訳を務めていた時の監督は、ドイツ人のマルコ・ローゼ監督でしたね。
宮沢 まずオーストリアの人とドイツの人を比べて思うのは、ドイツ人って、本当に負けず嫌いだということ。もちろん人によってその度合いは異なるのですが、比較的、言い訳が多い(笑)、負けを認めない、一回負けたら次に勝つためにどうしたらよいかを合理的に考える、そういう人種だと個人的には思っていて、それは、僕がドイツに来ようと考えた「ドイツ・サッカーがなぜ強いのか」の疑問を解き明かす上での大きなヒントになりました。
ーローゼ監督は現役時代に、いま南野選手がプレーしているリバプールで指揮を執っているユルゲン・クロップ監督の下、ドイツのマインツ05というクラブでプレーしていた経験がある方ですよね。
宮沢 そうです。だからかどうかは分かりませんが、監督として見た場合に、クロップ監督と似ているところがあると思います。例えば選手と一緒にパーティーができる、まじめだけじゃない、オフ・ザ・ピッチでも選手との距離が近い監督でした。リバプールに移籍した南野選手と電話で話してクロップ監督のことを聞いても、やはりローゼ監督と似ているところがあるのかなと思います。指導においては、しっかりとしたゲームプランがあって、基本原則は変えないけれどもゲームごとにフォーメーション、ボールの運び方や選手の立ち位置を変えながら自分たちのサッカーを表現する監督。シュテーガー監督と比べれば、細かい監督、と言えますね。
ー二人の監督を比べると、シュテーガー監督の方が大雑把に思えて、それで結果を残せるのだろうか、と疑問がわきます。
宮沢 私は通訳として2シーズン、シュテーガー監督のチームに携わらせて頂きましたが、その間、チームは2部リーグをほぼ負けなしで優勝して、昇格した翌年は1部に残留させています。勝つから良い雰囲気に、良い雰囲気だから勝てた、ということができると思うのですが、選手の自主性を重んじてそういう空気をつくり出したのが、シュテーガー監督の手腕ですし、そのおかげで長澤選手、大迫選手も積極的にプレーすることができたんじゃないかと思います。控えの選手を含めて、毎日楽しそうに練習をしているのを見ると、選手の良さをうまく引き出すための一つのアプローチとしてアリなんだろうな、と僕は感じました。

ーケルンのあと、ザルツブルクに行くことになるわけですが、その経緯は?
宮沢 ドイツで指導者A級ライセンスを取った時に、レッドブル・ライプツィヒの分析担当と意気投合して、ライプツィヒでチームのスカウトをやってみないかと誘われました。ですが、僕は指導者になりたいから、とお断りしたんです。そうするとザルツブルグの方に話が行って、そこからお誘いをいただいて、その時はまず南野選手の通訳としてのお誘いだったのですが、自分は指導者になりたいので数年後に育成年代の指導者としての道はあるのか、それと日本でS級ライセンスを取得したいのだがその支援は受けられるかといったことを交渉して、認められたので、ザルツブルグで仕事をするようになったのです。
ードイツでも育成年代での指導において、人間形成の面を意識することがありますか?
宮沢 もちろんあります。でも日本との違いはそこに『遊び』があるかどうかだと思います。遊びは、『どれだけ失敗が許されるか』ということです。もちろんその度合いは、クラブ哲学や指導者の指導哲学によって変わりますが、その許容範囲はドイツを含めたヨーロッパでは寛容だと思います。でも、そこが厳しいからこそ、日本人の規律正しさや、まじめさなど、世界から称賛される特徴が備わる、それは間違いないことだとも思います。でも、それがプロ・スポーツにおいて全員に必要かと問われれば、僕は「違う」と答えます。
ーその遊びは、育成年代でも必要だと思いますか?
宮沢 思います。僕も日本人ですから、そういう部分は厳しくしたいとは思っていますし、よく考え直すことでもあります。ワールドカップの決勝のピッチに立つチームの選手すべてが、几帳面で細かいことができる選手なのだろうか、と。やはりそこには範疇を越える”変な選手”がいないと、チームとしてそこにはたどりつけないだろうなと思いました。その変な選手を育てるために、『遊び』は不可欠だろうと、今の僕は考えています。
ー2019年に日本のS級指導者ライセンスを取得されたのはなぜでしょうか?
宮沢 ドイツに来る前、僕はいずれ日本に戻って日本サッカーを強くすることに貢献したいと考えていました。それに加えて今では日本の指導者の価値をヨーロッパで高めたいという思いも出てきました。そのためにはヨーロッパで日本のS級にあたる、プロ・ライセンスを取得する時にS級取得者であることがプラスに働くかもしれないと考えたのです。そのプロ・ライセンス取得は非常に難しいと思います。アジア人であるし、元プロ選手でもないし、かなりのハンディがあると分かっていますが、そのハンディを何とか乗り越えてライセンスを取得したいんです。
ー通訳として日本を代表する選手と接する中で、同様に世界の舞台で活躍できる選手を育成するための何かヒントになるようなものを手にしましたか?
宮沢 これをすれば、というものはないと思います。例外がたくさんあるのがサッカーですし、それがサッカーの大きな魅力でもありますから。先の話の“変な選手”というところにもつながってくると思うのですが、日本から海外に出て活躍する選手たちはみな『一芸』を持っていると思います。オープンマインドと負けず嫌いは選手ではなく、われわれ指導者を目指す者には必須だと思います。そして、海外に残れる選手は恐らく、自己分析がとても上手で、自分に足りないものと自分の武器の両方をしっかり把握して、それについて、練習で克服し、地道な努力でさらに伸ばしていける選手だと思います。短所だけに目を向けるのではなく長所も意識するバランスは大事でしょうね。なぜなら、こちらの指導者は「この選手はこれができる」、と長所に目を向けることが圧倒的に多いからです。そして、僕はそういう指導者が良い指導者になれるんじゃないか、と思うようになりました。
ーでは、次の指導者の方をご紹介ください。
宮沢 ドイツでの試合で対戦チームのコーチとして知り合った松岡裕三郎さんをご紹介します。VfBシュツットガルトのU-14とU-15チームで GKコーチを務めていらっしゃる方です。
<プロフィール>
宮沢 悠生(みやざわ・ゆうき)
1985年8月28日生まれ。
京都府出身。桂高校から、びわこ成蹊スポーツ大学に進学。大学ではスポーツ・マネジメントを専攻。大学卒業後の2009年に指導を学ぶためにドイツに渡る。FCケルンのパートナークラブでのジュニア、ジュニアユース年代の指導を続けながらケルン・スポーツ大学でも学び、指導者A級ライセンスを取得。FCケルンで長澤和輝選手や大迫勇也選手の通訳を務めた後、オーストリアのザルツブルグで南野拓実選手の通訳を務め、2018年から同クラブのアカデミーコーチとしてU-15の指導を担当、今年から昨年指導した選手を持ち上がる形でU-16チームのコーチを務めている。2019年には日本のS級ライセンスを取得済み。
text by Toru Shimada