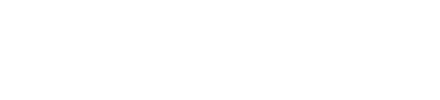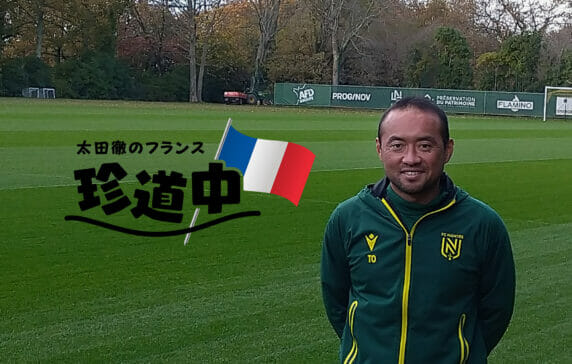愛知県の東の玄関口、豊橋市で28年前から活動をしているジュニアユースチームのセントラル豊橋FCは、チームの指導方法や選手の取組む姿勢から、多くの指導者の注目を集めている。新幹線の停車駅でもある豊橋駅からほど近い小学校のグラウンドで練習するチームの代表、内藤靖夫氏にその指導スタイルや理念についてお話を伺った。
ー内藤さんのこれまでの経歴をお聞かせいただけますか。
内藤 僕が監督を務めるセントラル豊橋FCは28年前に立ち上げました。きっかけは、学校の教員になり始めた時になかなか自分の思うように部活動での指導ができなかったので、卒業させた子らの保護者の強い要望もあり、だったら中学生のチームを立ち上げようということで始動しました。スタッフは僕も含めて皆小学校や中学校、高校の教員と接骨院の先生で、全員ボランティアでチームを見ています。
今チームが練習しているグランドは僕が新任で5年間勤めていた小学校で、その後は中学校の教員をしているのですが、28年間ずっとナイターでグラウンドを貸して頂いています。中学校で放課後の16時から18時まで部活のサッカー部の練習を見て、19時から21時までクラブの子達を見るという二足の草鞋なのですが、他のコーチも同様に、学校の仕事を終えてから練習に来てくれています。
練習は3年生が平日に2回と土日で週4回、1年生と2年生は平日にもう1日個人練習日を設けていて、そこに地域の小学生も参加して無料で中学生と一緒に練習をするという活動もしています。この取組はスペインのFCバルセロナ育成の合宿所から名前をとって、「ラ マシア」というスクール名で5年前から活動しているのですが、中学生みたいにうまくなりたい小学生を集めて一緒にサッカーをしようということで、大人は一切指示を出さず子どもたちに開放するという形です。
中学生は個人目標を自分で設定して練習し、そこに小学生が一緒に参加するという形ですが、中学生1人に対して小学生2,3人でボールを奪いにいくなど、中学生は小学生相手にどこまでできるかチャレンジになりますし、小学生は中学生の技や駆け引きを肌で感じることができます。同級生だけでなく、年上の選手に自分の技が通用するかとか、技を真似して身につけようとかできる環境が昔は空き地や公園であったと思いますが、今はそれができなくなっているので、そうした環境をつくっています。
ーご紹介いただいたイルソーレ小野FCの今村嘉男さんとのご縁はどういったものでしたか?。
内藤 僕たちは8年ほど前までは、県ベスト4や東海大会、全国大会を目指したチーム強化を主としていました。チームをさらに変えていかないといけないと考えていた時に、奈良県のディアブロッサ高田FCのフェスティバルに参加したのですが、そこでイルソーレ小野FCの子どもたちを見てこのチーム面白いなと思ったのがきっかけです。その当時は技術やスキルにこだわって強いチームを目指してやっていましたが、イルソーレやディアブロッサ、千葉県のVIVAIO船橋SCの選手たちはそれを超越したレベルでした。また両チームとも指導者がベンチからあれこれ指示を出しているわけでもなく、比較的選手に任せているのに対し、僕らはベンチから指示をかなり出していたのでこの違いに気付かされました。そこからチームのコンセプトをガラッと変えて取り組んで今に至るので、今村さんとの出会いは非常に大きかったです。
その頃僕はA級ジェネラルライセンスを取得したり、愛知県の三種技術委員長や国民体育大会の愛知県少年男子チーム監督を務めたり、県や東海トレセン活動も見ていました。そうした活動を通して全国のいろいろな指導者と交流する中で、街クラブがJクラブのアカデミーと同じことをしていても、いろいろな意味で勝てないなと思いました。そこで街クラブにできることは何だろうと考えた時に、街クラブにしかできないことをスタッフと一緒に模索しながら今の形にたどりついたという形です。
この街クラブにしかできないことというのはいろいろあると思いますが、一番は子どもの尖っている部分も含めて個性を大切にしてあげられるというところが核だと思っています。もちろん僕らも試合の勝負にこだわっていますが、「勝ち方」が優先されると、子どもの尖った部分が活かされないと思うので、「個」を大事にしてあげることが街クラブの良いことかなと思います。初めはチームのコンセプトを変えるのは勇気が必要でしたが、取り組むうちに街クラブにしかできないことを楽しくやっていこうと思い始めましたね。

ー今村さんとイルソーレとの出会いが大きなきっかけになったのですね。
内藤 間違いないですね。他にも特色があって面白いなと感じるチームに出会った時は指導者の方に「また胸を貸してくださいね」とお願いするのですが、そこで快諾をいただけた際には、僕たちは必ず足を運んできました。いろいろなチームの良い所見て学んで、子ども達には上には上がいるということを体験して肌で感じてもらうのが一番だと思っています。
また、子どもたちの方が僕たち大人よりもサッカー選手のイメージとして素敵な絵を描けています。指導者をしていると「あの選手のこういうプレーがすごい」とプレーモデルを示してしまいがちですが、もともと子どももセンスや才能を持ち合わせているということをベースに考えています。それに僕らが中高生の頃はサッカー中継を見るのも一苦労でしたが、今の子どもはスマホで簡単に世界中のサッカーを見ることができるので、イメージは子どもたちの方が豊かです。その上で子どもたちが持つ、「できる」というイメージや才能、資質を信頼してそこを環境で伸ばしてあげたら、僕らがイメージする選手なんかよりもっと凄い選手になるのかなと思います。だから教えるのではなく、その子が持っている資質や経験値を活かして引き出していこうというスタンスが良いのかなと思います。
今の子どもたちはチーム設立当時の子どもたちと比べて持っている情報量が圧倒的に違います。今は映像が溢れているので、ビデオテープが擦り切れるほど同じ映像を見ていた僕らの頃と比べて情報に対してこだわりがなくなってしまっている部分もあります。飽和してしまうと子どもたちも与えられるのが当たり前になってしまうので、情報を小出しにしながら子どもたちが行き詰まっている時に有効なものを見せたりする工夫が必要です。
同様にトレーニングも与えるのではなく、ゲーム形式の中から少し場面を引き出してトレーニングしていったら、後に自然と「こういうことか」と子どもたちが気付けるようになってくれればいいかなと思います。そういった情報もやたらに与えるのではなく、ピンポイントで与えてあげて、この場面のことなのかなと感じてもらえるようにしないといけません。
ー今はスマートフォンを開けば簡単に情報や映像が見ることができますね。
内藤 子どもたちにもスマートフォンが普及したことで、面と向かった言葉でのコミュニケーションが苦手な子が昔より増えたとは思います。ですがサッカーに自立している子はスマホの使い方も心得ているし、親も躾けられているので、サッカーが伸びる子はそういうことも自分で気をつけていますね。僕と1年生の監督を務める夏目和紀は同じ高校出身なのですが、「自ら考え自ら成す」という校訓だったので、自分で考えて自分で創作しないと、実力にもならないし、何より生き方に繋がらないという考えが根底にあります。なのであまりチームの規律を細かく作ってはいません。もちろん放任ではありませんが、「自ら成す」というところがサッカーや人として生きていくときにどう繋がってくるかといった話をしています。
こうしたことはサッカーに非常に影響すると考えていて、たとえばそのゲームの流れを掴むところからピッチ内の選手が感じてサッカーをしてくれています。3年生になると試合中に指示を仰ごうとしてベンチを見ることはあまりなく、ピッチ内にいるメンバーで解決していこうとします。それは練習でも僕らが答えを示さないので、子どもたちで解決策を見出すという習慣にはなってきているのかなと思います。
「セントラルのサッカーはこうだ」と決めるのではなく、状況に応じて変幻自在に自分たちのスタイルを変えることができるというのは僕たちの究極の目標です。相手が凄く上手い場合には引かないといけない時もあるし、この選手を抑えられないという時には1人ではなく2人でいくとか、引いて守ってカウンターを狙うなど、試合の中で変わる流れに対して「子どもたち」が察知して、今こうだからこうしようというように自分たちで判断できるように、練習の中でも試合の状況設定したようなトレーニングをしています。ハーフタイムもスタッフはあまり話さず、選手同士で打ち合わせをして、最後に僕が確認するという程度です。前半の試合展開で「ハーフタイムにはこういう話をしよう」と用意していても、3年生になるとだいたい同じことを選手も感じて話してくれています。僕の指示が間違っていた時もあったりして、ピッチにいる選手の方が正確に掴んでいるということがあるので、自分が指示を出すより選手が感じたようにすり合わせた方が良い展開になったかもしれないな、ということもあります。
イルソーレの選手を見るまではこうした方法も模索している状態でしたが、イルソーレの今村さんや選手たちを見て、「徹底して個を磨ききる」方向で間違っていないと確信を持つことができましたし、これが街クラブにしかできないことなのかなとも思いました。

ー全国大会出場などチームの目標は監督から話されるのですか?
内藤 私が目標を決めて選手に伝えるのではなくて、選手がそういう目標を持っている学年ならばそこに行くためにどうしようかとか、そこから逆算して考えていこうと声をかけています。勝ち上がることを優先して考えていれば、もうちょっとやり方も考えますが、監督も選手も負けていいとか負けて悔しくないと思っている人はチームに1人もいませんし、試合をする以上は勝つのが当たり前で全員が勝ちたいと思ってやっています。子どもたちの中で全国大会に行こうとか、そこを目指そうとかいう声が出てきた時には、そこから逆算して今はどれくらいの力かとか、この位置から強くなっていくには「個だけ」を我慢しないといけないとかを子どもたちに感じさせていて、そういう場面は大人の出番かなと思いますね。

ーご自身の指導力を磨く為に取り組んでいらっしゃることはありますか?
内藤 いろいろな情報がたくさんありますが、足を運んで経験したり、直接自分の目で確かめたりすることは心がけています。指導者ライセンスを取得する時には協会指針に沿って勉強していましたが、やはり本物というのは読んだり聞いたりするだけでは本当のことを吸収しきれないので、本当に良いのか、プラスになるかならないかは実際に足を運んで見てみないと分からないと思っています。ですので総体日本一になるまでの広島観音高校の畑喜美夫先生に学びに広島まで行きましたし、女子選手が常盤木学園高校に進学したいというので仙台まで行って練習を見学して、阿部由晴先生がどういった指導をされているのか、高校生はどういった取組でサッカーをしてなでしこ代表になっていくのかを拝見して吸収させて頂きました。中学校の部活ではサッカー部だけでなくバレーボール部の顧問を務めた時期も強いチームの所に行って練習の様子を見せて貰ったりしてその空気を肌で感じましたし、地元に駅伝の強い高校があったのですが、日本一を目指すチームの練習で、監督の後ろに立って選手に何を伝えるのかを学ばせていただきました。聖和学園高校の加見成司先生の選手への向き合い方は、今のセントラルの礎になっています。聞いたことだけでは絶対に子どもたちに伝えることはしないので、実際に足を運んでその空気を一緒に体感した上で、これだと思ったものしか子どもたちを本気で刺激できるものはないなと考えています。
反対に素晴らしい指導者やスカウトの方々が実際に足を運んで練習の様子とか試合を生で観に行かれるのだから、僕らはもっとそういう事をやらないといけないなと思います。サッカーもテレビ中継と生観戦では全然違いますよね。3年生の春休みには海外遠征にも出かけていて、そこでヨーロッパ選手権といった本気の試合をスタジアムで観戦するのですが日本とはスケールが違います。僕が中学生だったらちょっと寝むれないと思うので、そういう意味では今の子は恵まれていると思いますね。

ーチーム設立からまもなく30年になりますが、この先の展望はありますか?
内藤 将来Jリーガーになる選手や世界に羽ばたいていくような選手を育てたいという考えはあります。そうした考えの根底には、老子の「三略」にある言葉で「柔よく剛を制す」という考え方がサッカーにも当てはまるのではないか、日本人はそういうサッカーをしていく方が世界では通用するのかなと思う部分があります。一流の選手でもヨーロッパの選手に体格で勝てる日本人はなかなかいないと思うので、日本人特有のしなやかさや機敏さ、体を上手く使って、相手の力を自分の力に変えていくというような、そういうプレースタイルをこれから選手たちが身につけてくれると、その先少しくらい身体が小さくても世界で通用するのかなと思います。柔よく剛を制すといったことが子どもたちに芽生えて、プレーも考え方もしなやかで柔軟に対応できるような選手を育てていきたいですね。
そして街クラブにしかできないことをもっと特化して、いろいろな人がその選手のプレーや判断を見た時に「この選手ってもしかしたらセントラル出身?」とか「セントラル出身の選手ってこんな感じだよね」というような、プレーの内にスタイルがしみ込んでいて、誰が見てもセントラル出身者だとわかるような選手になってくれるといいなと思います。それが地域の中、豊橋の中で認知して頂いて、豊橋にはセントラルというチームがあるよ、あそこの選手って独特だよ、というように地域に取組の特徴が認知される街クラブというのが理想です。

ー最後に、次にバトンを渡していただく指導者の方をご紹介ください。
内藤 東海大学付属静岡翔洋高等学校の太田恒治先生です。中等部のサッカー部を指導されていた時に練習試合も何度もさせていただいているのですが、歴史ある強豪校にあって勝利が命題とされる中でも選手1人ひとりを大切に育てておられ、チームを通じてその熱意がすごく伝わってきますし、勉強させていただいています。
セントラル豊橋からも選手が進学させていただいていますが、選手やスタッフのみならずOB会からも信頼が厚い指導者なので、ご本人の指導に対する考えなどぜひお話を伺いたいです。
ーありがとうございました。
<プロフィール>
内藤靖夫(ないとう・やすお)
1967年6月12日生まれ。
豊橋市出身。小学生からサッカーを指導する父親の影響でプレーを始める。愛知教育大学では全国地域対抗サッカー選手権(現デンソーチャレンジカップ)に東海北信越代表として出場。卒業後は小学校の教員として務めていた1992年にセントラル豊橋FCを設立。転勤し中学校の教員となった後もチームを率い続けている。かつては愛知県サッカー協会三種技術委員長や県トレセン指導スタッフを務め、愛知県のサッカー発展に尽力してきた。内藤氏の指導を慕い、現在は豊橋市だけでなく周辺の市からも選手が集まり、全国の強豪高校や大学、Fリーグで活躍する選手を多く輩出している。
text by Satoshi Yamamura