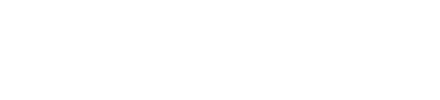父の背中を見て指導者に憧れ、その憧れを“頑固に”持ち続けて、今は大宮アルディージャのU15カテゴリーの中でU13を担当する育成指導者に――。夢を実現させるまでの道のり、自らを“庶民的レベルの指導者”だと言う、その指導姿勢や指導理念についてお話を聞かせていただきました。
ーまず始めに、筑波大蹴球部の小井土正亮監督からご紹介していただきました。小井土監督とのご関係について教えてください。
横谷 小井土は筑波大大学院の同級生の一人です。小井土は当時、体育心理学を専攻していて、僕はコーチ学を専攻していたので研究室は違いました。でも、院生の最後の年に補助学生という形で僕ら筑波大生がJFAのS級ライセンスの講習会のサポートをすることになりました。そのサポート学生のチーフに小井土がついて、僕はそこに参加していた補助学生の一人として、その講習期間中に濃い時間を過ごした仲です。
ー小井土さんから横谷さんは育成年代の指導にものすごい熱量で取り組む方だと聞きました。まず、なぜ育成年代の指導者になったのか、お聞かせください。
横谷 とても光栄なお言葉で恐縮です。僕の父親はサッカー選手でした。柏レイソルの前進である日立製作所サッカー部に所属していたサイドバックで、日本代表キャップも持っています。年齢的には西野朗(元日本代表監督)さんの一つ上だと聞いていますが、一緒の時代に日立でプレーしていました。父は僕にサッカーを強要することは一切なかったのですが、勝手に父に憧れてボールを蹴るようになりました。僕自身は選手として大したことなくて、それは練習が嫌いだったからだと思うのですが(笑)、まあそれはいいとして、父が現役を引退したあとに『日立サッカースクール柏』(現在の柏レイソル・アカデミー)で、育成年代の選手を指導するようになって、僕もそのクラブでボールを蹴っていたので、父が指導する姿をいつも間近で見ていました。その時の様子、選手とのやりとりとかを見る中で、指導者への道を意識するようになりました。そのころ僕はまだ小学生だったと思いますが、選手になれなかったとしてもサッカーに携わる仕事をしたい、その中でも指導者になれたらなぁ、なんて思っていたんです。
ーそのころの思いが中学、高校、大学になっても変わらなかった?
横谷 そうなんです。自分でもよく分からないのですが、頑なな性格なんでしょうかね、そこの思いは変わらなかった。選手としては不本意な出来でしたが、大学まで一生懸命にサッカーをやったのは、指導者になった時のために、プレーヤーとしての経験を積んでおこう、という考えからでした。
ー大学院卒業後に京都サンガF.C.の育成普及部。その後にドイツに渡ったんですね?
横谷 京都サンガF.C.ではサッカーのいろははもちろん、指導者としての基礎を学び、そしてたくさんの大きな出会いをしてきました。今の自分の礎はこの時期に築かれたと言っても過言ではありません。その一方で、僕は「キャプテン翼」に憧れた世代なんですが(笑)、小さい頃からそこで見た海外への挑戦に強い憧れを抱き続けていて、そういうイメージを持つ中で、一度、海外で指導経験を積みたいなと考えていたんです。その思いが強くなったタイミングでクラブにお願いして辞めさせていただいて、ドイツへ。同時にこの頃から強い興味があったオランダの指導哲学、指導メソッドに触れるために、住みやすさと学びやすい環境を考えて、ドイツの、そしてオランダに近い、デュッセルドルフという街に住もうと決めました。
ーデュッセルドルフではどんなチームで指導を?
横谷 デュッセルドルフは日本人が多い街としても有名ですが、そこにいらっしゃった日本人の方に『ISDe.V』を紹介していただいたんです。そこはデュッセルドルフ市にあるインターナショナルスクール直属のクラブでして、その学校の部活動のような立ち位置でしたが、でも、ちゃんとチーム登録をしてリーグ戦を戦っています。そこで日本人のスタッフを探しているということで、僕はU-10チームを担当して、1シーズン半ほど指導をさせていただきました。
ードイツでの2年間は勉強になりましたか?
横谷 具体的な指導方法とか哲学が学べたことはもちろんありますが、それ以上に自分の“人間味”に大きな影響を与えてくれたといいましょうか。例えば、これはサッカー指導者にかかわらず、どんな仕事をしていても、その人の生きざまが仕事に染み出てくる、という感じがあるじゃないですか? そういう意味で、多くの理解や協力のおかげで2年弱もの時間をドイツで生活できたことが自分の人間的な豊かさにじんわりとつながっていて、それが今、指導者となった自分の支えになっているし、実際に指導する場面でもなんらかの影響が出ていると信じています。もちろん、例えばオランダでは『インターナショナル・コーチングコース』という、当時2週間ほどのカリキュラムの講習会に参加したりして、サッカーの指導にかかわる勉強もすごく充実していましたが、今、指導現場に立ちながら身に染みて実感することが多いのは、ドイツやオランダでの日常生活で学んだこと、出会った人たちから得た人としての器や温かみの方が大きいように思います。

ードイツで言葉の問題は?
横谷 日本で多少は勉強していったのですが、まったく通用せず(笑)。だから向こうでドイツ語学校に通って初歩から学んで、3カ月くらいしてからマシになって……。そのころに、先ほどのデュッセルドルフでの指導の話をいただいて、勉強の成果が出せると思ったら、指導は「英語でやってくれ」と(笑)。まあ、それはそれで結果として英語の勉強になって今に役立つ場面もあったりして、人生、何が幸いするかわからないものですね……(笑)。
ー指導する上で、言葉は大切になると思うのですが?
横谷 当時確かにボキャブラリーの面では不自由しました。ただ、文法が間違っているとか、表現方法が間違っているんじゃないかと心配するんじゃなくて、当時は「上手に、ではなく、まずは伝えよう、伝えたいんだ」というスタンスだけを心掛けていたように思いますね。さらに、そこに自分の熱量が入るように。
ー言葉と熱量の関係でいうと、日本に帰ってきてから、言葉が通じる分、言葉に頼る部分が増える、ということにはならなかったのでしょうか。
横谷 もともと僕は話をするのが好きなので正直、頼りがちかもしれません(笑)。なのでどうしても、論理的にサッカーを語ろうとすると、指導者ではなく“解説者”になりがち。指導することと、ゲームを見て分析したり、解説したり、人に何かを説明することは大きく違うんだ、ということは自分なりに意識するようにしています。根本的に考えると、日本語にはいろいろな表現があって、比喩なども充実しているという素敵な特長がある中で、どうしても口数が多くなるとか、文章が長くなるとか、が起こりがちですよね。そして日本語は前置きがあって最後に結論を持ってくる特徴をもちます。でも、外国語は基本、最初に結論がバンって来て、その後に「なぜならば…」と短く続く。そこは外国語を参考にしながら、日本語として結論は最後に持ってくるにしても、前置きをシンプルにして結論を目立たせるとか、小さな工夫をところどころに意識した方がいいのかもしれませんね。一方でそれが行き過ぎると、どこかこざっぱりと冷めた感じになってしまい、子どもや選手に指導者の熱量が伝わりきらないこともあるかなとも思います。僕の場合は熱くなりすぎてボリューム多くしゃべってしまう傾向にあるので、熱量をうまく乗せることと、端的に説明する、アドバイスを送る、というところのバランス調整は、永遠のテーマになるのかもしれません(笑)。

ー育成年代での指導者を志してドイツに渡り、でも帰国されてからは大宮アルディージャとヴァンフォーレ甲府のトップチームの分析担当を務めましたね?
横谷 まず、非常に有難いご縁であり、チャンスであったということが大きいです。特別な経歴を持ち合わせていない“庶民レベル”の僕にとっては、 プロクラブのトップチームで仕事ができる機会はそうなかなかないでしょうし、プロを目指そうとする子どもたちを指導する時のことを考えると、やはり僕がプロの世界を見て、直にプロ選手に接しているのと、いないのとでは、プロ選手経験のない自分にとって、それを補うという意味でも、その差は大きいだろうな、と。実際、Jの各クラブに1人の割合で分析担当がいたとして計算し、今のJ1から、U-23の2チームを除いたJ3までのクラブ数で言うと、日本サッカー界で56人しか就けない仕事と捉えられるんですよね。そういう意味でも、とてつもなく価値のある経験になるだろうと考えて、ありがたく引き受けさせていただきました。
ーいま、大宮ではU13のご担当です。U13に所属する中学1年生への指導で気を付けている点は?
横谷 サッカーの基礎づくりはもちろんのこと、成長期の差し掛かりなのでケガや障害などの身体のところ、そして小学校から中学校に上がって生活スタイルが変わるので精神面でもケアしてあげなければいけない年代だと思っています。ましてや練習も時間や強度が変わるので、慣れるための猶予を与えてあげることも意識しています。そして何もなければU15チームまでの3年間をアルディージャでプレーすることになるので、1年間で完結を目指すのではなく、中学校3年目やさらにその先の未来で結実するための、さまざまな土台づくりの時期でもあるというところを考えてながら接していく必要があると感じています。また、ほかのクラブから新たに加入してくる子どももいるので、プロのクラブに所属する意味や、そこでどんな振る舞いをしなくちゃいけないのかなど、ピッチ内外の価値基準を整えてあげて、サッカー選手である自分の成長を自分で促進していけるような学びにつなげてあげたいと思っています。
ー育成年代の指導において、大宮ならではの特徴はありますか?
横谷 もともとピム・ファーベークさんが大宮のトップチームの初代監督を務められた時に、オランダの論理性高いフットボール哲学が導入され、そこから端を発して今のアルディージャの哲学の歴史が築かれていると聞いています。そして僕もそこに憧れてこのクラブにお世話になっている一人です。日本だけで、ではなくて世界からもニーズがあるような選手に育てるためのサッカーの基本的な考え方、捉え方、ボールの扱い方、戦術的なところも含めて、サッカーを論理的に整理して指導しているのが、アルディージャのアカデミーの大きな特徴だと思います。近隣には資金や人気、実力を兼揃えたとても大きなクラブが多くあるという環境下において、僕たちは自身の存在の小ささと存在意義を正しく認識して、いろいろな知恵、情熱でほかのクラブとの違いを出すという意味で、論理性の高いサッカーというものが、われわれの大きな武器になっていると考えていますし、それがクラブの一つのアイデンティティーになっていると思います。

ー今のお話を聞いて納得したことが一つあります。今季の大宮のトップチームには、昨季まで期限付き移籍という形で他チームにおいて武者修行を積んできた選手がいますよね。水戸で経験を積んだ黒川淳史選手、同じく18年まで水戸でプレーした小島幹敏選手や、J3のいわてグルージャ盛岡とブラウブリッツ秋田でプレーした藤沼拓夢選手など。彼らが大宮とは異なるスタイルの他チームで良いパフォーマンスを発揮できたのは、さきほどの論理的な指導をアルディージャのアカデミーで受けたことで頭の中が整理されているからではないかと思いました。
横谷 もちろん彼らにも僕らには分からない苦労と努力があったと思いますが、所属したチームで良いパフォーマンスを発揮できる優れた柔軟性を持つ選手たちであることは間違いないと思います。そういう意味では、アカデミー時代に彼らの指導に携わってこられた指導者の方々が彼らに必要な武器、どこでも生き抜いていける能力を備えさせたのだと思います。いま名前が挙がった選手以外に、今季トップチームで登録されている選手の半分近くが大宮のアカデミー出身者です。
ーFC東京や東京ヴェルディといった老舗のクラブのアカデミー出身選手の多さに匹敵するレベルにまで来ましたね。
横谷 9月末にU18所属の大澤朋也と柴山昌也の2名が来季からのトップチームへの昇格が決まりましたが、彼らが中学2年生の時、僕も指導を担当させてもらいました。実際のところは僕が彼らに特別何かをしてあげられたわけではないので申し訳ない気持ちも大きいのですが、いろんな方々の、さまざまな働きかけのおかげでいろいろな武器を持たせてもらっているのは事実で、彼らが次に続いてくれているのは、すごく誇りに思えますね。
ー今後、どういう指導者になりたいですか?
横谷 僕はいま、こういう年代に働きかけるという仕事が楽しくて、喜びをいただいています。だからダイヤの原石である選手たちに対して、少しでも良いアプローチをして、良い選手になるサポートをすること、またプロ選手になれなくても社会の中で、ここでの経験を礎にしながら生きていけるような指導ができればなと思います。また先ほども言いましたが、僕は庶民レベルのコーチを自認しているので(笑)、地域の方々に近づきやすいコーチだと思っていただければうれしいですし、そうして生きていく末には、育成の職人と呼ばれるようなスペシャリストに憧れているので、そこを目指したいと思います。

ーそれでは、次の指導者の方をご紹介ください。
横谷 京都サンガF.C.時代にお世話になった、川勝博康さんをご紹介します。育成の副部長を務められた後、いまは僕と同じU-15カテゴリーのU-13担当コーチを務められている方です。
<プロフィール>
横谷 亮(よこたに・りょう)
1979年3月18生まれ。
千葉県出身。千葉英和高から明治学院大へ進学。明治学院大卒業後に筑波大大学院でコーチ学を専攻。大学院在学中に、『ピュアネスサッカースクール』で指導者への道に入る。京都サンガF.C.の育成普及部コーチを務めた後に指導理論を学ぶためにドイツに渡り、『ISDe.V.U10』のコーチを務める。帰国後、大宮アルディージャの分析担当(2年間)、ヴァンフォーレ甲府のコーチ兼分析担当(6年間)。2016年から大宮アルディージャに戻り、アカデミー指導者になり、現職に至る。
text by Toru Shimada