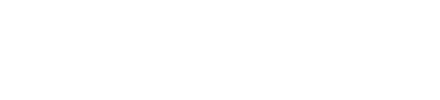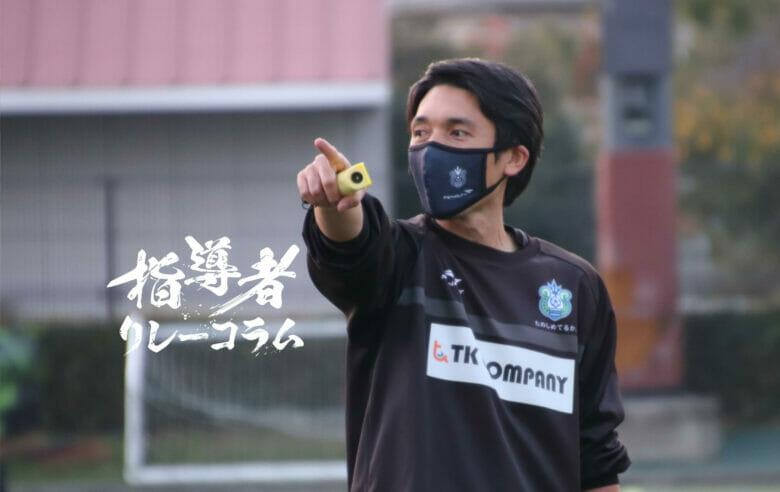CATEGORY 指導者リレーコラム
Vol.43 湘南ベルマーレU-15 監督/山口貴弘
現役時代、最も長い時間を過ごしたクラブで、曺貴裁監督という偉大な存在に出会った山口貴弘さん―。影響を受けた指導者のように情熱と愛を持った指導者になるべく、湘南ベルマーレU-15監督として模索を続ける日々、選手との向き合い方に迫った。
Vol.42 ツエーゲン金沢 ユース監督/辻田真輝
クラブスタッフの熱意に心を揺さぶられ、選手としてツエーゲン金沢発足メンバーとなった辻田真輝さん。JFL昇格に貢献したものの、チームのあり方に疑問を感じ、それは25歳にして指導者の道に入るきっかけともなった。指導歴は10年を超え、ツエーゲン金沢U-18や石川県国体チームの監督として「石川の立ち位置」を上げるために尽力している。現役時代から1年間の社会人生活、そして指導者として貫き続ける考えに迫った。
Vol.41 鹿児島ユナイテッドU-14 監督/デイビッドソン・純・マーカス
鹿児島ユナイテッドFCのU-15クラスでコーチを務めるのが、アメリカと日本の二重国籍を持つデイビッドソン純マーカスさん。現役時代にJリーグでの出場を重ね、アメリカに渡ってからは、その多岐にわたる文化や、個性を一つにまとめあげる指導者の存在に魅力を感じるようになった。指導者への意欲が芽生え、再び日本に戻ってセカンドキャリアをスタートさせたマーカスさんに、指導の楽しさや貫き続ける信念をうかがった。
Vol.40 松本山雅FC U-15監督/須藤 右介
本田圭佑さんに誘われ、Soltilo Chiba FCという新しい街クラブで、29歳にして指導者デビューした元Jリーガーの須藤右介さん。現在はかつて所属した松本山雅FCユースアカデミーで、地元の選手を中心に指導をしている。選手として、指導者として、社長として、営業マンとしていつか戻りたい―。松本山雅を選手たちにとって特別な「ロイヤリティのあるクラブ」にしていくため、指導者として模索する日々についてお話をうかがった。
Vol.39 エスペランサSC 代表/オルテガ・グスタボ
横浜に希望を―。「日本の青少年の自殺率が高いことに心を痛め、スポーツを通して日本の子どもを助けたい」という願いから元アルゼンチン代表のオルテガ・ホルヘ・アルベルトさんを中心につくられたエスペランサSCは、創設19年目を迎える。創設当時から父であるアルベルトさんの下でコーチを務め、現在はクラブの代表、トップチームコーチ、U-13、U-15の指導も行うオルテガ・ホルヘ・グスタボさん。現在川崎フロンターレで活躍する脇坂泰斗選手も輩出したクラブで、指導において大切にする理念をうかがった。
Vol.38 中国広州城U-14監督/上村健一
現役時代はサンフレッチェ広島などでセンターバックとしてプレーし、引退後はロアッソ熊本のアカデミーコーチなどを経てカマタマーレ讃岐のトップチーム監督も経験。現在は中国の広州城(前年まで広州富力)で中学年代を教える上村健一さんにお話をうかがった。成功体験のみならず、苦い経験も糧に、新しい環境での指導に挑戦中の上村さん。中国でのサッカー文化、そこでの指導が日本サッカー界に与える影響、そして自身の中にあり続ける選手への向き合い方とはどういったものなのか―。
Vol.37 アサンプション国際中学・高校コーチ/足高裕司
長きに渡りガンバ大阪で育成の哲学を学び、中国・広州富力のアカデミーコーチとして海外挑戦も。プロの選手経験はなくとも、自分だけにしかない経験を還元したい。現在は大阪のアサンプション国際中学高校で指導にあたる足高裕司さんに、これまでの経験で感じたことや自らの中に起こった変化についてうかがいました。
Vol.36 ガイナーレ鳥取U-15監督/畑野伸和
指導者になる目標を胸に大学での4年間、コーチとしての1年間を過ごし、鳥取の地へ再び戻ってきた―。ガイナーレ鳥取で子どもたちが「夢中になれる空間」「輝ける環境」を作ろうと奮闘する指導者に、夢を志すようになったきっかけやこれまでの経験、指導におけるやりがいについて聞いた。
Vol.35 ファジアーノ岡山U-15コーチ/大西容平
生まれ故郷である岡山に戻り、現在は中学生の指導に励む大西容平さん。一人でも多くの選手をトップチーム、日本代表、そして世界へと輩出したい―。時代の移り変わりとともに見える選手の変化、そして自身の現役時代にはなかった自分の中に押し寄せてくる感情についても、赤裸々に語ってくださいました。
Vol.34 ヴァンフォーレ甲府U15監督/津田琢磨
地域リーグの舞台でプレーをしたことが、指導者の道に進むきっかけとなった。ヴァンフォーレ甲府で幼稚園生から高校生と様々な年代での指導を経て、現在はU-15(ジュニアユース)チームの監督を務める。楽しむことを教える幼稚園生、高校生への進路指導…。あらゆる経験が指導者としての引き出しを増やしてきた。現役時代の大半を過ごした特別なクラブで、「日々新しいことを見つけたい」と自分流の指導のあり方を模索する。これまでの2年間、そしてこれから先についても語ってもらった。